河辺林通信−−−建部北町の森から ’00年2月号 No.21
★新しい年の作業はこうして始まった
 南の入り口は工事中で進入できず、東の駐車スペースに車を置くと竹藪がない! 森の中に入るといつものダイニングルーム(?)から、竹藪が無くなり向こうが丸見え! そんなわけで今回はみんなで工事現場の観察からスタート。広場やネイチャーセンター予定地の竹藪を切り開いた現場では、ケヤキやコナラなどの高木だけが残されて開放的な空間が誕生しており、夏の木漏れ日を想像する人や今更ながらに竹の多かったことに感心する人、台風での倒木を心配する人、それぞれに何かを感じられたようです。観察から戻って来ると、山田親方が手回しよく火を起こし竹筒(?)を温めておりましたとさ。竹筒の先には注ぎ口に細工がしてあり、感心してしまいます。(?:カッポ酒)
南の入り口は工事中で進入できず、東の駐車スペースに車を置くと竹藪がない! 森の中に入るといつものダイニングルーム(?)から、竹藪が無くなり向こうが丸見え! そんなわけで今回はみんなで工事現場の観察からスタート。広場やネイチャーセンター予定地の竹藪を切り開いた現場では、ケヤキやコナラなどの高木だけが残されて開放的な空間が誕生しており、夏の木漏れ日を想像する人や今更ながらに竹の多かったことに感心する人、台風での倒木を心配する人、それぞれに何かを感じられたようです。観察から戻って来ると、山田親方が手回しよく火を起こし竹筒(?)を温めておりましたとさ。竹筒の先には注ぎ口に細工がしてあり、感心してしまいます。(?:カッポ酒)
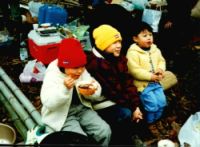 実施した作業は、人海戦術での落葉掻き、炭焼、導入した機械を使用しての薪作りと残枝の粉砕、残したい木へのテープ巻きと餅を利用した昼食準備です。今回は地元の建部北町の方をはじめ50人ほどの方が参加して下さいました。京都や大津からも森林ボランティア・メンバーが、造林公社の紹介で参加、ボクちゃんを先頭に家族で落葉掻きに専念していただきました。温かい昼食にとても喜んでいただけたようです。次回も参加をお待ちしています。
実施した作業は、人海戦術での落葉掻き、炭焼、導入した機械を使用しての薪作りと残枝の粉砕、残したい木へのテープ巻きと餅を利用した昼食準備です。今回は地元の建部北町の方をはじめ50人ほどの方が参加して下さいました。京都や大津からも森林ボランティア・メンバーが、造林公社の紹介で参加、ボクちゃんを先頭に家族で落葉掻きに専念していただきました。温かい昼食にとても喜んでいただけたようです。次回も参加をお待ちしています。
★チッパーと薪割機の威力
12月に導入した機械の本格的な稼働を行いましたが、それぞれの状況をお知らせします。まずチッパー、今までかさばっていた残枝の量を減らすことについては抜群の威力を発揮していますが、処理できる量が少なく林床管理作業で発生する残枝の量との釣り合いがとれないということです。薪にできるものは薪にして有効利用を計る必要があるようです。新しく作った囲いの底に網を敷いたのは、モグラ(インゴロ)にカブト虫の幼虫(ガット)を食べられないためです。モグラが見つけると食糧倉庫に住み着くような案配になってしまいます。薪割機は、構造はシンプルですが、危険性もほとんどなく面白いように薪を作ってくれます。建部北町のメカ好きの小林さんは感心するやら、イッチョ自分でも作ったろうかという顔で作業を進めておられました。できあがった薪がきちんと積み上げられると、私なんかは昔の生活を知っている者ですので、すごく豊かな気持ちになってしまいました。
★ボランティア総合保険に加入
冬の林床で春を待つスミレ

|
前号でお知らせしていましたが、「遊林会」活動時のメンバーの事故に備えて保険に加入しました。保障内容は、入院(1日につき)
5,000円 通院(1日につき) 3,000円 死亡・後遺障害 1,000万円です。お世話にはなりたくないですが、いざというときに皆さんの活動に対して少し報いることができるようになりました。保障内容には、目的のための往復途上も含まれています。年間保険金額は
70,200円で、遊林会会計(他に出すとこなんてあるのかよ?)より支出しました。大丈夫です、まだ2〜3回分の活動費は残っていますし、毎回、誰かが少しまとまった金額をいろんな理由で寄付して下さいます。ありがとうございます。(これからもよろしく。)
今年は、財政確立が課題です。
★試験的に週日の活動を計画
 炭焼き名人の城さんは、工事で伐られ処分されていく竹が可愛そうでなりません。一部でも炭に焼いて成仏させてやらにゃーという思いのようです。炭焼きにも良いシーズンです。1月の竹炭は硬質で良いのが焼けたようです。炭焼きやチッパーの稼働、工事が進む森の点検等をするために、課題であった週日の活動を計画しました。2月2日(水)、雨天の予備日2月3日(木)でやりましょう。都合の付く方の参加をお待ちしています。
炭焼き名人の城さんは、工事で伐られ処分されていく竹が可愛そうでなりません。一部でも炭に焼いて成仏させてやらにゃーという思いのようです。炭焼きにも良いシーズンです。1月の竹炭は硬質で良いのが焼けたようです。炭焼きやチッパーの稼働、工事が進む森の点検等をするために、課題であった週日の活動を計画しました。2月2日(水)、雨天の予備日2月3日(木)でやりましょう。都合の付く方の参加をお待ちしています。
★昔の森の話・・・アラカシの利用・・・
 林床作業の中では、他の植物の成長を阻害して生命力の強い常緑樹の代表として、親の敵のような扱いを受けているアオキやアラカシですが、アラカシは堅い材質ですので、何かに使われていなかったのかと気にかかっていました。余談ですが、アオキは自転車の虫ゴムを使ったパチンコ(私の所では、ゴムチュウと言っていました)のY字型の部分に使うくらいでした。プランツ・ハンターによって日本から持ち込まれたヨーロッパでは観葉植物として珍重されましたが、最初は雄の木だけしかなくて赤い実のできる雌の木を持ち込んだ者は大もうけをしたという話を聞いたことがあります。所変わればの話です。一方のアラカシは、調べてみると利用方法がありました。八日市では炭を焼いたという話は聞いていませんし、農家では、普段、炭を使うということは無かったようですが、こたつ(瓦と同じ材質の立方体で蓋付きの豆火鉢のような物。炭や木炭を熱源として利用)などに炭の代わりにアラカシの薪を使っていたようです。あまり太くない枝を短く切って火鉢の灰の中に埋めて、上に”おくどさん”で煮炊きに使って中まで充分に火が回った薪の細片を置いておくと夕方にはアラカシの木片は中まで真っ赤におこっており、そのままこたつの灰の中に入れたり消して良質の消炭として炭の代用にしたようです。成長する前に適当な太さで利用したようなので萌芽する性質と併せてアラカシは森の中で株立ち状態で生えていたようです。樫ですが、あまり器具材には使わなかったとのことです。他の利用法があればお知らせ下さい。
林床作業の中では、他の植物の成長を阻害して生命力の強い常緑樹の代表として、親の敵のような扱いを受けているアオキやアラカシですが、アラカシは堅い材質ですので、何かに使われていなかったのかと気にかかっていました。余談ですが、アオキは自転車の虫ゴムを使ったパチンコ(私の所では、ゴムチュウと言っていました)のY字型の部分に使うくらいでした。プランツ・ハンターによって日本から持ち込まれたヨーロッパでは観葉植物として珍重されましたが、最初は雄の木だけしかなくて赤い実のできる雌の木を持ち込んだ者は大もうけをしたという話を聞いたことがあります。所変わればの話です。一方のアラカシは、調べてみると利用方法がありました。八日市では炭を焼いたという話は聞いていませんし、農家では、普段、炭を使うということは無かったようですが、こたつ(瓦と同じ材質の立方体で蓋付きの豆火鉢のような物。炭や木炭を熱源として利用)などに炭の代わりにアラカシの薪を使っていたようです。あまり太くない枝を短く切って火鉢の灰の中に埋めて、上に”おくどさん”で煮炊きに使って中まで充分に火が回った薪の細片を置いておくと夕方にはアラカシの木片は中まで真っ赤におこっており、そのままこたつの灰の中に入れたり消して良質の消炭として炭の代用にしたようです。成長する前に適当な太さで利用したようなので萌芽する性質と併せてアラカシは森の中で株立ち状態で生えていたようです。樫ですが、あまり器具材には使わなかったとのことです。他の利用法があればお知らせ下さい。
★「河辺いきものの森」情報
森の中では、ネイチャーセンターや広場の部分の工事と森林作業員による管理用道路と観察路、立ち枯れた木の処分、竹の除去が急ピッチで進められています。観察路の工事では重機を木や植物の少ない所に誘導しながら進めたり、枯れ木の処分を重機を使って集めると林床のダメージが大きいのでその場で切り刻むように変更を求めたり、作業員に残す木と伐る木のミーティングを実施したりともう一人のヒゲは大忙しです。森林観察デッキの足場では、ケヤキとクヌギを残すべくきめ細やかな掘削をしています。竹の抜根が必要な部分では、木の根本までして木を痛めないように2メートルの除外地を設定したりもしています。(春にタケノコ退治をお願いします。)それでも、完全には納得できないのが実状です。後、今年度中に屋外便所(浄化槽接続の関係で来年まで使用できません。)、駐車場、浄化槽工事を実施します。
工事は一度限りのこと、その後、変化するこの森を活かすも殺すもわれわれのボランティア活動次第だと工事現場を前にして思わずにはおれません。
★2月の作業予定
「遊林会」の活動は、緑の募金を国レベルで運用している国土緑化推進機構によって各地の森林ボランティア活動として印刷物やインターネットでも紹介されていますが、1月の欄で思わず吹き出してしまいました。活動内容(予定)に落葉掻、薪づくりに続いて「新年会」と紹介されていたのです。私達の毎月の活動を熟知した上での記載かと感心もいたしましたが、まぁ、いつものやり方が認知されたとしておきましょう。
2月の作業では、いつもの作業に加えて竹の筒作りをします。理由は → この森では、竹がなかったところに竹が進出した部分で工事作業員による竹の伐採が進められています。竹を除いてしまうと一部の高木を除いてほとんど何も植物がありませんので、南高生の実習で森の中の実生を移植する予定ですが、移植する部分は裸地になっており雑草の繁茂が懸念され、刈払機の使用が必要になると思われます。その際に移植した実生苗が刈られてしまうので、苗の周りに輪切りにした竹のプロテクターをしてみようと考えました。最初は、ペットボトルを考えたのですが、村松氏から竹を使えよというアドバイスがありましたので、なるほどと考えた次第です。
いつも食事をしているアラカシの周りですが、参加者が増えてきて、新しく来られた方などは離れた所で食事をしておられるようなケースが目立ちます。座れる場所を拡大して、やはり参加者みんなで輪になって食事をするのが「遊林会」のやり方だと思います。少しその辺の工夫もしたいと考えています。
★2月の昼食のこと
 ビデオを撮影されている大西さんの所には鶏がいるのですが、愛着が出てしまいなかなか本来の目的のために利用できずになっているようです。あのソメヤンハサケガスキー氏が聞きつけ(本人も自分の飼っていた軍鶏には天寿を全うさせたようですが。)、任しといて、他人さんの飼っていたのならいつもさばいているのでということになったらしいです。そんなわけで、2月は鶏三昧、きりたんぽ鍋はどうかとも考えています。きりたんぽはご飯をつぶして焼いた物ですので、冷やご飯の差し入れ歓迎します。野菜も歓迎です。
ビデオを撮影されている大西さんの所には鶏がいるのですが、愛着が出てしまいなかなか本来の目的のために利用できずになっているようです。あのソメヤンハサケガスキー氏が聞きつけ(本人も自分の飼っていた軍鶏には天寿を全うさせたようですが。)、任しといて、他人さんの飼っていたのならいつもさばいているのでということになったらしいです。そんなわけで、2月は鶏三昧、きりたんぽ鍋はどうかとも考えています。きりたんぽはご飯をつぶして焼いた物ですので、冷やご飯の差し入れ歓迎します。野菜も歓迎です。
発行者:八日市市緑町10-5 八日市市役所 花と緑の推進室内 遊林会 世話役 武藤精蔵 Tel 0748-24-5658
▲前の号 |
河辺林通信トップ |
次の号▼
| ホームに戻る |
 南の入り口は工事中で進入できず、東の駐車スペースに車を置くと竹藪がない! 森の中に入るといつものダイニングルーム(?)から、竹藪が無くなり向こうが丸見え! そんなわけで今回はみんなで工事現場の観察からスタート。広場やネイチャーセンター予定地の竹藪を切り開いた現場では、ケヤキやコナラなどの高木だけが残されて開放的な空間が誕生しており、夏の木漏れ日を想像する人や今更ながらに竹の多かったことに感心する人、台風での倒木を心配する人、それぞれに何かを感じられたようです。観察から戻って来ると、山田親方が手回しよく火を起こし竹筒(?)を温めておりましたとさ。竹筒の先には注ぎ口に細工がしてあり、感心してしまいます。(?:カッポ酒)
南の入り口は工事中で進入できず、東の駐車スペースに車を置くと竹藪がない! 森の中に入るといつものダイニングルーム(?)から、竹藪が無くなり向こうが丸見え! そんなわけで今回はみんなで工事現場の観察からスタート。広場やネイチャーセンター予定地の竹藪を切り開いた現場では、ケヤキやコナラなどの高木だけが残されて開放的な空間が誕生しており、夏の木漏れ日を想像する人や今更ながらに竹の多かったことに感心する人、台風での倒木を心配する人、それぞれに何かを感じられたようです。観察から戻って来ると、山田親方が手回しよく火を起こし竹筒(?)を温めておりましたとさ。竹筒の先には注ぎ口に細工がしてあり、感心してしまいます。(?:カッポ酒)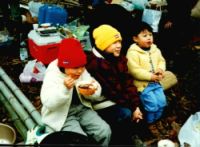 実施した作業は、人海戦術での落葉掻き、炭焼、導入した機械を使用しての薪作りと残枝の粉砕、残したい木へのテープ巻きと餅を利用した昼食準備です。今回は地元の建部北町の方をはじめ50人ほどの方が参加して下さいました。京都や大津からも森林ボランティア・メンバーが、造林公社の紹介で参加、ボクちゃんを先頭に家族で落葉掻きに専念していただきました。温かい昼食にとても喜んでいただけたようです。次回も参加をお待ちしています。
実施した作業は、人海戦術での落葉掻き、炭焼、導入した機械を使用しての薪作りと残枝の粉砕、残したい木へのテープ巻きと餅を利用した昼食準備です。今回は地元の建部北町の方をはじめ50人ほどの方が参加して下さいました。京都や大津からも森林ボランティア・メンバーが、造林公社の紹介で参加、ボクちゃんを先頭に家族で落葉掻きに専念していただきました。温かい昼食にとても喜んでいただけたようです。次回も参加をお待ちしています。
 炭焼き名人の城さんは、工事で伐られ処分されていく竹が可愛そうでなりません。一部でも炭に焼いて成仏させてやらにゃーという思いのようです。炭焼きにも良いシーズンです。1月の竹炭は硬質で良いのが焼けたようです。炭焼きやチッパーの稼働、工事が進む森の点検等をするために、課題であった週日の活動を計画しました。2月2日(水)、雨天の予備日2月3日(木)でやりましょう。都合の付く方の参加をお待ちしています。
炭焼き名人の城さんは、工事で伐られ処分されていく竹が可愛そうでなりません。一部でも炭に焼いて成仏させてやらにゃーという思いのようです。炭焼きにも良いシーズンです。1月の竹炭は硬質で良いのが焼けたようです。炭焼きやチッパーの稼働、工事が進む森の点検等をするために、課題であった週日の活動を計画しました。2月2日(水)、雨天の予備日2月3日(木)でやりましょう。都合の付く方の参加をお待ちしています。 林床作業の中では、他の植物の成長を阻害して生命力の強い常緑樹の代表として、親の敵のような扱いを受けているアオキやアラカシですが、アラカシは堅い材質ですので、何かに使われていなかったのかと気にかかっていました。余談ですが、アオキは自転車の虫ゴムを使ったパチンコ(私の所では、ゴムチュウと言っていました)のY字型の部分に使うくらいでした。プランツ・ハンターによって日本から持ち込まれたヨーロッパでは観葉植物として珍重されましたが、最初は雄の木だけしかなくて赤い実のできる雌の木を持ち込んだ者は大もうけをしたという話を聞いたことがあります。所変わればの話です。一方のアラカシは、調べてみると利用方法がありました。八日市では炭を焼いたという話は聞いていませんし、農家では、普段、炭を使うということは無かったようですが、こたつ(瓦と同じ材質の立方体で蓋付きの豆火鉢のような物。炭や木炭を熱源として利用)などに炭の代わりにアラカシの薪を使っていたようです。あまり太くない枝を短く切って火鉢の灰の中に埋めて、上に”おくどさん”で煮炊きに使って中まで充分に火が回った薪の細片を置いておくと夕方にはアラカシの木片は中まで真っ赤におこっており、そのままこたつの灰の中に入れたり消して良質の消炭として炭の代用にしたようです。成長する前に適当な太さで利用したようなので萌芽する性質と併せてアラカシは森の中で株立ち状態で生えていたようです。樫ですが、あまり器具材には使わなかったとのことです。他の利用法があればお知らせ下さい。
林床作業の中では、他の植物の成長を阻害して生命力の強い常緑樹の代表として、親の敵のような扱いを受けているアオキやアラカシですが、アラカシは堅い材質ですので、何かに使われていなかったのかと気にかかっていました。余談ですが、アオキは自転車の虫ゴムを使ったパチンコ(私の所では、ゴムチュウと言っていました)のY字型の部分に使うくらいでした。プランツ・ハンターによって日本から持ち込まれたヨーロッパでは観葉植物として珍重されましたが、最初は雄の木だけしかなくて赤い実のできる雌の木を持ち込んだ者は大もうけをしたという話を聞いたことがあります。所変わればの話です。一方のアラカシは、調べてみると利用方法がありました。八日市では炭を焼いたという話は聞いていませんし、農家では、普段、炭を使うということは無かったようですが、こたつ(瓦と同じ材質の立方体で蓋付きの豆火鉢のような物。炭や木炭を熱源として利用)などに炭の代わりにアラカシの薪を使っていたようです。あまり太くない枝を短く切って火鉢の灰の中に埋めて、上に”おくどさん”で煮炊きに使って中まで充分に火が回った薪の細片を置いておくと夕方にはアラカシの木片は中まで真っ赤におこっており、そのままこたつの灰の中に入れたり消して良質の消炭として炭の代用にしたようです。成長する前に適当な太さで利用したようなので萌芽する性質と併せてアラカシは森の中で株立ち状態で生えていたようです。樫ですが、あまり器具材には使わなかったとのことです。他の利用法があればお知らせ下さい。 ビデオを撮影されている大西さんの所には鶏がいるのですが、愛着が出てしまいなかなか本来の目的のために利用できずになっているようです。あのソメヤンハサケガスキー氏が聞きつけ(本人も自分の飼っていた軍鶏には天寿を全うさせたようですが。)、任しといて、他人さんの飼っていたのならいつもさばいているのでということになったらしいです。そんなわけで、2月は鶏三昧、きりたんぽ鍋はどうかとも考えています。きりたんぽはご飯をつぶして焼いた物ですので、冷やご飯の差し入れ歓迎します。野菜も歓迎です。
ビデオを撮影されている大西さんの所には鶏がいるのですが、愛着が出てしまいなかなか本来の目的のために利用できずになっているようです。あのソメヤンハサケガスキー氏が聞きつけ(本人も自分の飼っていた軍鶏には天寿を全うさせたようですが。)、任しといて、他人さんの飼っていたのならいつもさばいているのでということになったらしいです。そんなわけで、2月は鶏三昧、きりたんぽ鍋はどうかとも考えています。きりたんぽはご飯をつぶして焼いた物ですので、冷やご飯の差し入れ歓迎します。野菜も歓迎です。